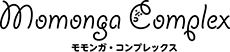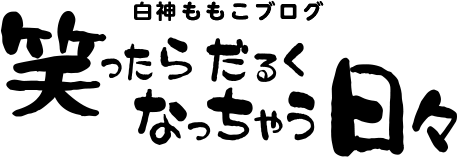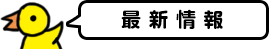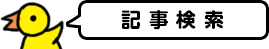那覇文化芸術劇場なはーと 出会いシリーズ2『花売の縁オン(ザ)ライン』無事に終演し、一ヶ月とちょっとの沖縄滞在を終えて東京に戻ってきました。
観に来てくださった皆さま、気にかけてくださった皆さまありがとうございました。そして、キャスト、スタッフ含めたくさんの方々が知性とセンスと能力を諦めることなく注いでくださったことに感謝しています。
企画の土屋さん、シマシマ企画の島袋さんには2月のリサーチの時いやそれ以上前から最後の日まで大変お世話になりました。
なんだかいろいろなことが泡となって消えないうちに今回のことを書いておこうと思いました。(長くなりそう、気をつけて!あと、誤字脱字とか語尾の不揃いとか堪忍な)
この作品は沖縄公演のみでしたので、観れなかった方も多かったと思うので少し解説。元になった組踊の『花売の縁』という演目は、高宮城親雲上という人の作品で、失踪した父親探しに出た母と息子が父を探して主にその親子の再会が描かれていて、その道中に猿回しの芸人に会ったり(猿引き)、その父親の居所を知っている老人(薪取り)に会う、みたいな話です。(ざっくり)
私が思うポイントとしてはこの演目は、中心から少し外れた人たちが出てくる。首里などではなく大宜味村という沖縄の北部の地域が描かれ、生活が苦しい落ちぶれた士族の家族(核家族が描かれていることもポイントby兼島氏)、旅の芸人、お年寄り、という特に力を持たぬ普通のひとたち。複雑な構成でも華やかなわけでもないですが、道行きの情景の美しさが琉歌の八八八六調のリズムにのってゆったり染み入ってくる体感型の作品。(だなと初見は思いました)
戦後すぐに収容所で上演され人々の心を癒した、沖縄の人たちにとってとても大切な作品でもあります。そんな大切な作品をよそ者の私が関わって何かして良いものかどうか、、と引き受けたものの最初は悩みもしましたが、、とりあえず風のまにまに(クロスプレイ東松山)の教訓で、外から来たものとして風を送り込む役割と思って挑みました。
で、
引き受けてからは、組踊そのものや琉舞の身体、そして組踊『花売の縁』と同時に沖縄・琉球のリサーチ・研究の日々が始まった。かと思いきや、否、むしろその辺のことはそこそこに兼島拓也研究が忙しくなったのは言うまでもなくw『ライカムで待っとく』はもちろん、ラジオドラマがあると言えば聴き、過去作品を読み返し、対談や彼が読んだと言う本は一通り読む努力(読んだところで追い付きはしない)、彼の劇団であるチョコ泥棒とそのメンバーについて、兼島さんと話して漏れ出る好物やオモシロワードを心のメモに刻んでいった。オタク気質なのでオタクよろしく。それは大げさですけど。(その後、俳優さんのリサーチも加わってきてこれも出会いシリーズの醍醐味だなと)
そうそう、物語の舞台となった塩屋リサーチは本当に充実していた。それは、なはーと公式サイトの兼島拓也による現地リサーチ・レポートを見てください。廃墟とか。
ただ何回目かの兼島さんとの逢瀬で、脚本の構想を聞いて「おやおや?」となり、脚本の第一稿が上がって来た時、あまりの濃密さとぶっとびに歯が抜けそうになった。なんだこれは。おい、話が違うぞ、兼島。
『花売の縁オン(ザ)ライン』は組踊『花売の縁』のストーリーにもう一つの異人館ストーリーが加わり、組踊を介して歴史から見た琉球の立場や欧州、中国、日本の思惑に翻弄される琉球・そして今にも通ずる沖縄の物語。異人館の要素として経済、アヘン、テレグラフなどの要素が渦巻き、人物もペリー、ラッセン、ノストラダムス、ジョン万次郎を始めとした各種ジョン、小野妹子、などが同時に出てくるスチームパンク的な設定。
私、歴史は好きなんですが、、テレグラフとか経済に一切興味がなかったので、第一稿を読んだときは何も分からず青ざめたわけ。台詞は面白かったんだけどね。。なんのことかさっぱりとなって8月の顔合わせと読み合わせ時点では発言だけははっきりとしていましたが、始終ハッタリで押し通し、舞台美術、衣装、音楽の打合せになっても何も確かな確信を持っていない状況だった。(爆)
そうしたみっちみちの情報量の脚本ではあるけれど、この劇作家の言葉と姿勢、作品の面白さは確かなもので、沖縄を描くことすなわち世界を描くことと感じた。で、私みたいなテレグラフなんかに興味ないわ、、、と情報量に諦めてしまいそうな人も楽しく観られるようにするのが感覚ビジュアル系としての私の仕事だわ!とこのみちみちの戯曲にすき間を適宜開け、プスプスと風を通して、兼島さんと共に美術の鈴木さん、音楽のjujumoさん、衣装のAco Miyagiさん、照明の棚原さんなどと協力して時間を紡いでいく作業が主になったと思う。
そして全体的に舞台上の身体の存在のさせ方として、組踊の身体にゆるさとおさえた表現が拮抗して存在すること、がまくと呼ばれる上半身の部分を繊細に使うことで、感情や俳優の状態が変わることなどを8月の神谷武史さんのレクチャーを通して体感、そして間近でその身体を観られたことがとても助けになりました。ここがポイントだと。(トークでお伝えしそびれて記憶を改ざんしたいほど悔やんでいる)

神谷武史さんによるレクチャー。歩き方や振る舞いを教えていただきとても良き時間でした。
不安に思っていた稽古は始まってみるととても楽しく、6名の俳優それぞれの色が全然違って、たくさんアイデアを各々の角度から提供してくれた。時間がない中、特に滞ることなく快活に進んだ。更に、音楽のjujumoさんが来る度に思いもしないアイデアと楽器と雑貨各種をもってきてくれて、違法建築のごとく独自の広がりと連なりと面白さが増した。

プロデューサーお手製の小道具類と共にjujumoさんが持って来てくれたひょうたんヘッドホン

チョコ泥棒流寝稽古中 乙樽&鶴松
兼島さんと共通するところとして『こうあるべき』が強くなるとそこにいられなくなる人ができてしまうことをお互い分かって創作している気がして、それは兼島さんの保育園を経営していた経歴やチョコ泥棒での積み重ねと元々が持つ大らかさによるものではと思いました。
ラストを単なるハッピーエンドにしないという作家としての姿勢にも貫かれたものを感じています。
私は、といえば、主に屁の如くプップとすきま風を入れていき、小ネタ大ネタと美しい情景を差し挟み、差し挟んでははしゃいでニタニタゲラゲラする日々だった気もする。。
なんの取り柄もないと思っていたけれど、、ん?そうだ、きっと私の一見無意味かつ無駄と思える言動はほぼ屁のようなものかもしれない。(最近詩人に読ませてもらった詩の影響かもしれない)
急に極端な表現になってしまったけれど、私たちは社会や世界にすき間風を作って生きやすくする役目があると改めて思ったという展開です。そしてそのすきま風は時に強くそしてゆるく、出るときは出るのだと毅然としている。まるで、屁。
そして、、、変な比喩になってしまうけど、安心して屁ができる空間すなわち劇場の意義。
わかった。(なにが)
私たちにできることは、「踊らされること」と「忘れられること」。そして、「時に屁をこくこと(さまざまなスピードと形で)」と追加しておこう。
勝手に。
![]()
![]()
![]()
公演写真と公演パンフレットがなはーとの公式サイト【こちら】に上がっていますのでぜひチェックしてみてください![]() アイデアにんべんさんのデザインも大好き。
アイデアにんべんさんのデザインも大好き。

本当に大好きな座組の皆さま。ラブ

あなたとわたしのA&Wを確かめに。モモコン北川は、お芝居あまりしないのに台詞頑張ってくれた。あとアシスタント。もう、足を向けて眠れない。

プロデューサーの土屋わかこさんから教えてもらい、琉球舞踊のワークショップへ。猿の踊りおしえていただきました。

本番前のなんかの時間。

みんな元気でかわいいメンバー。らぶ

かわいいw

一応、振付の仕事も。笠の段本当に素敵だったよ。

猿の二人もかわいかった。

かわいいnew 感謝

jujumoさんの島。コンセプトは違法建築だそう。

イケメン森川氏と謎の小学生味ある鶴松、そして衣装のAcoさんw

メイクの友寄さん。メイクの力を感じました。

宣伝美術のアイデアにんべんさんにいただいたステッカーと台本。ずっと作品に寄り添ってくださってありがたかった。

プロデューサー力作の道具。すごすぎ。らぶ